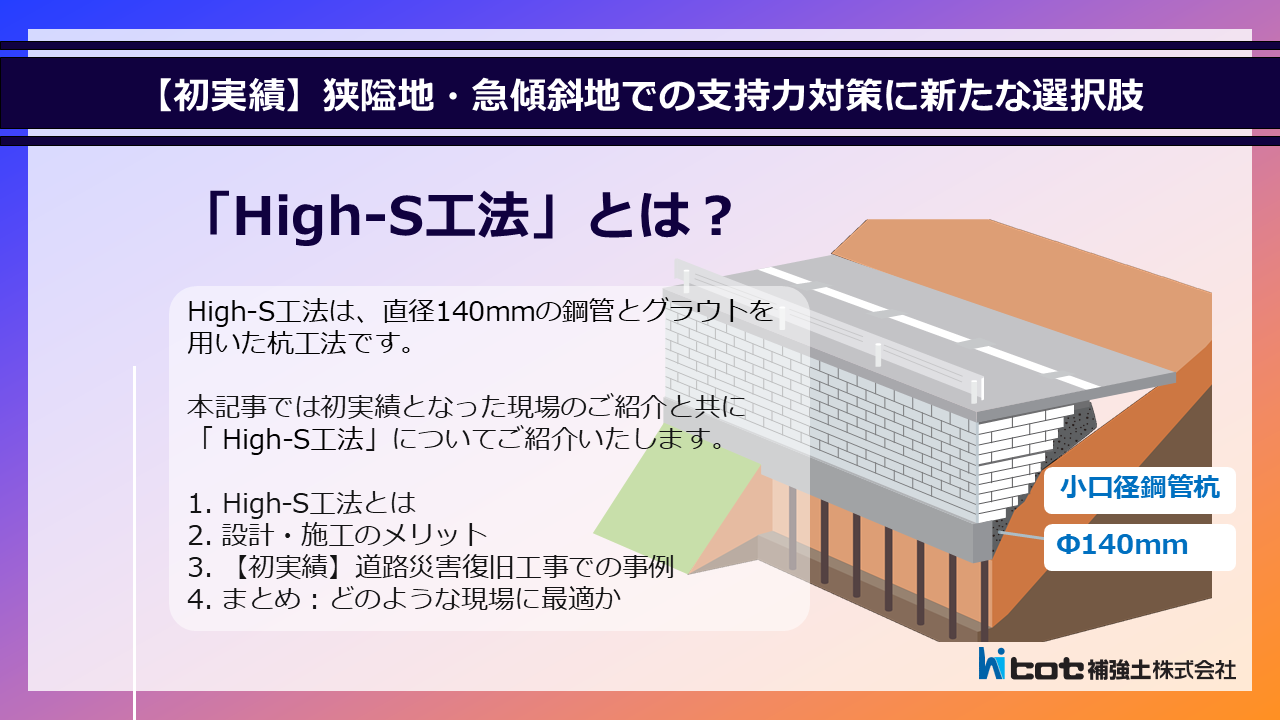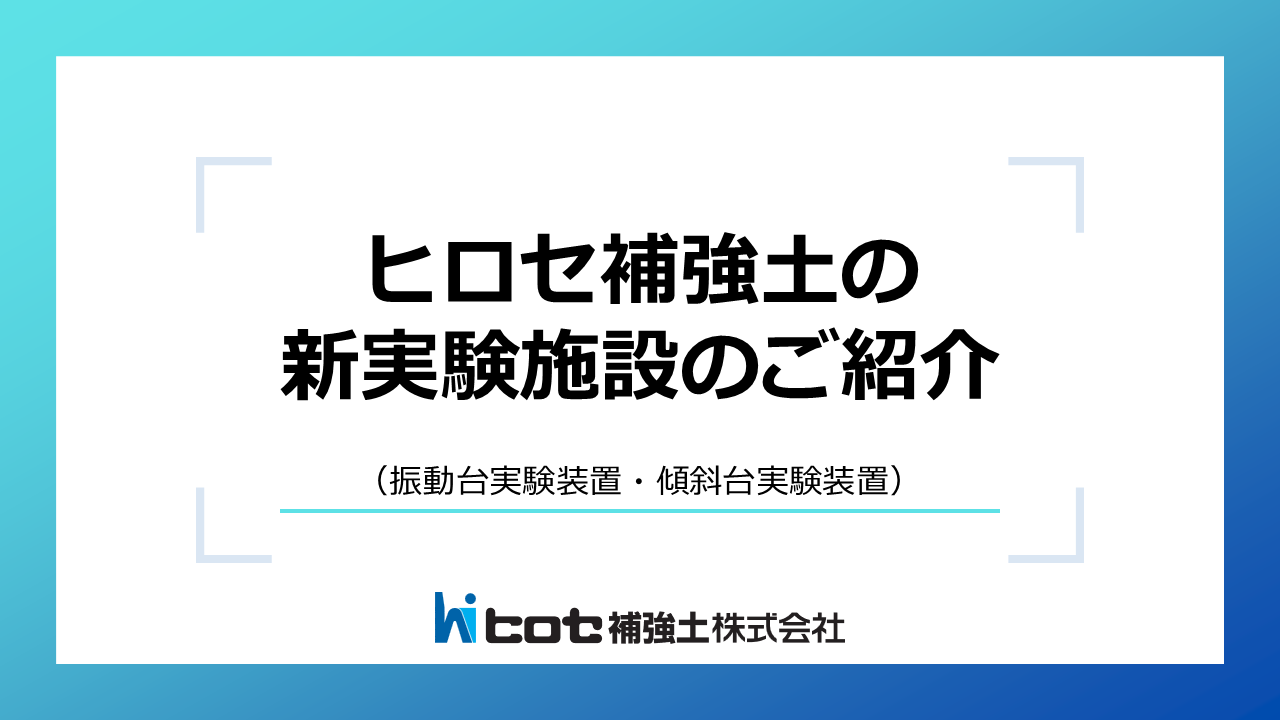「防災の日」に考える|社会インフラと建設業の役割
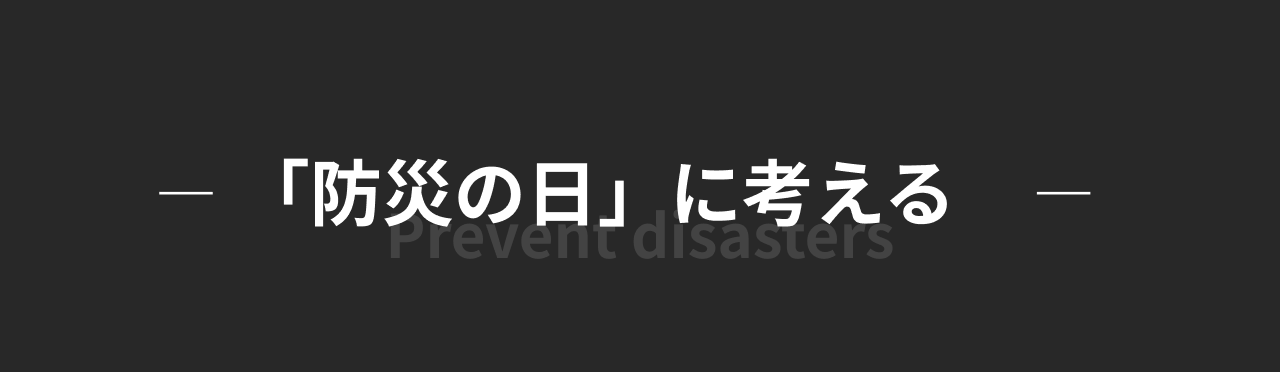
「防災の日」に考える|社会インフラと建設業の役割
9月1日の「防災の日」にちなみ、今回は災害と、いのちを守るインフラについて考えるコラムをお届けします。
「防災の日」の由来。激甚化する災害に対する「国土強靭化」に触れながら、改めて防災意識を高めるきっかけとなれば幸いです。
目次
- 9月1日は「防災の日」
- 道路や橋梁、トンネル、堤防などのインフラが災害時に担う役割
災害大国日本の新たな司令塔「防災庁」とは - 災害に負けない国づくり「国土強靭化」
ハードとソフト、両面からのアプローチ - 防災減災に貢献する建設業
- 道路の法面や擁壁補強など、土砂崩れや浸食を未然に防ぐ工事を行う意義
- 防災の日、心新たに考える
9月1日は「防災の日」
9月1日は防災の日です。この日は1923年に関東大震災が発生した日でもあります。日本はよく「災害大国」とも呼ばれますが、防災の日をきっかけに日頃から災害への備えをしてみようと考える方もいるでしょう。
関東大震災は、1923年9月1日の午後11時58分に発生しました。相模湾北西部を震源とし、地震の規模を示すマグニチュードは7.9で、東京を中心に関東一円で大きな被害を出しました。内閣府によると、死者行方不明者は10万5000人にのぼったとされています。また地震発生時刻がお昼近くだったこともあり、多くの地域で火災が発生。被害を受けた家屋は10万棟を超え、約55億円もの経済被害を受けたといわれています。

9月1日を防災の日にすることを制定したのが1960年。前年に発生した伊勢湾台風による死者4700人、行方不明者401人などといった大きな被害がきっかけとなりました。それから65年が経ちますが、暦の上での意味合いもあったことをご存知でしょうか。
実は、9月1日は暦の上では二百十日を意味します。立春から数えて210日を示し、農作物が台風など被害を受けてしまう可能性があるとして厄日とされていました。今となっては、この時期は、台風が日本列島を襲いやすい時期だとわかっていますが、当時は違う捉え方をしていたようです。
このように、ここ数年でも令和6年能登半島地震や先日発生したカムチャツカ半島沖の地震津波、それから九州地方での大雨、各地でのゲリラ豪雨・線状降水帯の発生など、自然災害は頻繁に発生し激甚化しています。これらの事実は、防災について考えるうえで触れておく必要があるのです。
道路や橋梁、トンネル、堤防などのインフラが災害時に担う役割
防災について考える際に重要視したいのが、インフラの役割です。特に道路やトンネル、橋梁、堤防などの社会資本は災害時にその機能を果たします。
例えば、道路や橋梁は傷病人を運ぶ際のルートであり、救援物資などを運ぶ命の道でもあります。道を覆うトンネルもそうですね。もし道が土砂崩れなどで塞がれてしまうと、傷病人や救援物資を輸送できなくなってしまいます。そうなれば、救助活動に向かう道が寸断されることになり、応急処置などにかかる時間が増えてしまいかねません。また救助に向かうことも不可能になり、被害が拡大する一因になってしまうのです。
それだけではありません。ダムや河川、堤防も重要なインフラのひとつです。冒頭でも触れましたが、日本では激しい大雨による土砂災害がほぼ毎年のように発生しています。記憶が新しいところでは、今年8月に発生した九州の土砂災害では、前線の影響により大雨が降った影響で数人が亡くなるなど被害が大きくなっています。昨年には、九州南部に上陸した台風10号によって土砂崩れが発生。気象庁の速報値によると、総降水量は東海地方や九州南部で900mmを超え、竜巻などの突風も発生したといいます。また関東から九州にかけては記録的な大雨を観測しました。
大雨によって河川の増水や堤防の決壊などもたびたび発生します。河川が増水した際には、必要によってはダムの緊急放流も行われます。それによってダムの貯水量を調整し、ダムを溢れさせない工夫がなされているのです。
さらに、河川の改修も大切です。河川が増水し、洪水が発生しそうになった際に堤防がその役割を発揮します。堤防の影響を利用して水が流れる断面を大きくすることで、洪水をできるだけ防ぐのです。また河川を掘り、水が流れる断面を大きくして水位を下げる河道掘削なども大きな効果を生み出します。
このような取り組みを通じて、災害を引き起こさせない対策がなされています。
災害大国日本の新たな司令塔「防災庁」とは
防災といえば、最近で動きが活発化している防災庁についても触れておきましょう。防災庁は、昨年の自民党総裁選挙に出馬した石破茂候補(現首相)が掲げていたものです。
昨年10月、石破内閣の発足とともに、防災庁の設置が内閣の基本方針として提示されました。その翌月、内閣官房に防災庁設置準備室を発足させています。そして今年1月末には防災庁の設置に向けた「防災庁設置準備アドバイザー会議」を開催。今後、政府は来年度から防災庁を発足させる方針を固めています。
ただこの防災庁、以前にも構想があったことをご存知でしょうか。2011年に発生した東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)後には、国会の議論の中でアメリカの事例を参考にした災害特化省庁を創設すべきとの意見が出ていました。また2020年頃から感染が拡大した新型コロナウイルスを受け、2023年に内閣感染症危機管理統括庁が設置。感染症から国民を守る司令塔として注目されました。
防災庁の設置は、林芳正官房長官が「事前防災を徹底し平時から不断に万全の備えを行ううえで意義がある」と昨年11月の記者会見で述べた通り、日本にとって重要な意味合いがあります。災害が沢山発生する国の司令塔として、どのような役割を担っていけるのかに注目が集まります。
災害に負けない国づくり「国土強靭化」
内閣官房では、国土強靭化と呼ばれる取り組みを進めています。内閣官房の資料によると、伊勢湾台風や1995年の阪神淡路大震災、2011年の東日本大震災などで得られた教訓を踏まえ、インフラ整備などを含んだハード対策と、情報発信などを含んだソフト対策を組み合わせ、総合的な対策の必要性が認識されたといいます。
国土強靭化とは、「大規模自然災害時に、人命を守り、経済社会への被害が致命的にならず、迅速に回復する『強さとしなやかさ』を備えた国土、経済社会システムを平時から構築していくこと」。基本目標は①人命の保護が最大限図られること②国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること③国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化④迅速な復旧復興の4つです。
2013年に議員立法で成立した「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法」から枠組みが作られました。その後、「国土強靭化基本計画」(2014年閣議決定、2018年と2023年に改定。おおむね5年ごとに見直し)、「防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策」(2018年閣議決定、2018年度から2020年度までの3年間)、「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策」(2021年度から2025年度までの5年間)と取り組みが進められました。
なお今年6月、政府は2030年までを計画期間とした「第1次国土強靱化実施中期計画案」を閣議決定。約20兆円を超える予算規模を予定し、発生が迫っているとされる南海トラフ巨大地震の対策なども盛り込んでいます。
では計画案の具体的な取り組みを見ていきましょう。対策にはハードとソフトの両面があります。
ハードとソフト、両面からのアプローチ
ハード面では、治山や治水、堤防強化、盛土規制、津波避難施設の整備などが挙げられます。例えば、インフラの整備・管理では、気候変動に伴って激甚化・頻発化する災害のほか、切迫しているとされる南海トラフ巨大地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震や火山噴火などから国民を守るとしています。また道路や鉄道、空港、港湾などの災害に耐える力を強くし、迅速な人命救助や避難、早期復旧・復興を支援。上下水道や電力などは地域の実情を踏まえながら持続可能なインフラへと再構築します。
堤防の強化では、気候変動を踏まえた高潮や津波に対応。ソフト面と一体の水災害対策で、河川流域全体で協働して連携する「流域治水」対策を進めています。また、災害に強い市街地をつくることを目的とした対策として、後述する津波避難施設(津波避難タワー)の整備なども挙げられています。
ソフト面では、ハザードマップの作成や配布、子どもたちへの防災教育、定期的な避難訓練などが挙げられます。
最近では、今年7月末にロシア・カムチャツカ半島沖で発生したマグニチュード8.7の地震によって津波が発生。一時は日本各地の沿岸部で津波警報や津波注意報が発令されました。高いところでは1.3メートル(岩手県久慈港)の津波が観測され、各地では避難が呼びかけられました。その際にはハザードマップの活用が多く呼びかけられ、避難場所の確認にも用いられました。
昨年1月1日には、石川県能登半島地方を震源とするマグニチュード7.6の地震があり、最大震度7を石川県の輪島市と志賀町で観測しました。石川県によると、今年3月末時点での被害は、死者549人、行方不明者2人、負傷者1267人となっています。住家被害は11万5681棟、最大の避難者数は3万4173人にのぼりました。この地震では津波も発生しました。福岡県の研究チームが発表した分析結果によると、津波の一部は海抜11.3メートルまで遡上していたといいます。地震と津波被害を受け、周辺地域ではハザードマップを作り直す自治体もあり、この被害を今後どのようにして教訓にしていくのかが問われています。
また昨年8月8日には、気象庁が初めて南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)を発表しました。同日に発生した宮崎県・日向灘沖で発生したマグニチュード7.1の地震を受けての発表でしたが、沿岸部では一時、緊張が高まりました。
政府の中央防災会議が想定している被害想定(今年3月)によると、最悪の場合、死者は29万8000人あまりにのぼるとされています。内訳は津波で21万5000人、建物の倒壊で7万3000人、火災などで9000人前後としています。想定される津波の高さが20メートルを超える沿岸部もあり、ハザードマップの活用や学校での教育、避難訓練を定期的に実施することで、情報共有を図ることが重要です。
防災減災に貢献する建設業
このような被害を少しでも軽減できるよう、様々な対策が図られています。そのひとつが前述した津波避難タワーです。ハード面でも少し触れていますが、津波避難タワーは高台などの避難場所までの距離がある場所に設置されている一時避難施設をいいます。
国土交通省によると、鉄骨の骨組みの上に一時的に避難できるスペースを設けているものが一般的だとしています。さらに同じような機能を持つ建物として、緊急的な一時避難場所の津波避難ビルなども挙げています。
そのほかの施設でも防災のための建て替えなどが行われています。国土交通省の「防災拠点等となる建築物の機能継続に係る事例集」によると、南海トラフ巨大地震による津波浸水想定エリアにある徳島県阿南市庁舎では、老朽化の影響もあって現在の位置で防災拠点施設として庁舎を建て替え。免震構造とし、浸水対策や液状化対策を実施して、災害対応を担う課を比較的高い階に集約し、災害対応時の拠点を守る構成にしたといいます。
宮城県では、2011年の東日本大震災で被災した北上運河(東松島市)の復旧が行われました。運河は震災の津波によって堤防が決壊し、甚大な被害を受けました。復旧作業では、今後発生するとみられる津波を想定し、堤防表面をコンクリートで覆うなどして、津波が堤防を越えたとしても破壊されない構造を実現しました。
このように、建設業や土木施工は災害復旧において大きな貢献を果たしており、防災大国ともいわれる我が国の社会資本を支えているのです。
道路の法面や擁壁補強など、土砂崩れや浸食を未然に防ぐ工事を行う意義
道路の法面や擁壁補強なども意味のあることです。法面補強は、特に大雨による土砂崩れを防ぐ役割があります。もし法面が崩れて土砂崩れが起きた場合、作業員らが土砂崩れに巻き込まれ、最悪、命が脅かされる可能性もあります。
東北地方整備局の資料によると、2018年度に発生した事例の中で、作業員1名が作業中に法面崩壊に巻き込まれ、骨盤骨折などで全治6ヶ月のけがを負った事例があるといいます。
擁壁補強も同様です。擁壁は強く頑丈でなければ、地盤がゆるくなったり擁壁が歪んだりした際にすぐ崩れてしまいます。河川の脇に整備されている河川護岸も、一旦崩れてしまえば、容易に浸食されてしまうことも考えられます。
昨年の能登半島地震では、地震の揺れによって住宅の擁壁が崩れる被害が相次いで発生しました。新潟県糸魚川市での宅地危険度では、167棟中76棟で危険と判定。避難を余儀なくされた住民もいたといいます。
このような事態を引き起こさないためにも、日ごろからこまめに点検を行い、必要であれば追加工事や補修、災害への対策を行うことが大切なのです。
(参考文献)
東京都消防庁 https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/learning/elib/qa/qa_59.html
内閣府防災情報 https://www.bousai.go.jp/kantou100/
NHK NEWS https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241101/k10014626351000.html
内閣感染症危機管理統括庁 https://www.caicm.go.jp/about/index.html
内閣官房第1次国土強靱化実施中期計画 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/dai1_chuukikeikaku/index.html
内閣官房国土強靭化推進室 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/suisinkaigi/joukyou_dai7/siryou5.pdf
首相官邸第1次国土強靱化実施中期計画 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokudo_kyoujinka/kaisai/dai23/siryou2.pdf
今年もまた迎える防災の日。過去幾多の災害を忘れないようにするだけでなく、建設業界に身を置く我々は現場に立って公共インフラや建物等を強靭にすべく取り組み続けています。それはこれまでの災害にも立ち向かったように、これからも誇りをもって安心な暮らしを支え続けることを誓いましょう。
次回も貴社に役立つ情報をご紹介していきます。
引き続き、皆様が気になる話題にお応えして参りますのでご期待ください。
こんな話題を取り上げてほしい、こんなことが気になる、などの
ご意見もお待ちしております。
今後とも何卒よろしくお願いいたします。
ご不明点やご意見・ご要望などお気軽にお問い合わせください
お問い合わせフォームへ